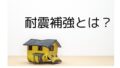最近よく聞くようになった「減災(げんさい)」という考え方を知っていますか?
「減災って何?」「防災とどう違うの?」と、疑問を持つ方も多いかもしれませんね。
実は、災害から命や暮らしを守るための方法は、「防災」だけではありません。「減災」も、私たちの命や生活を守るための方法の一つなんです。
その元となっているのは、地震や台風、大雨などの自然災害による被害を少しでも減らそうという考え方です。
とはいえ、「何をすればいいのかわからない」という方も多いかもしれません。
そこで、この記事では「減災と防災の違い」をはじめ、「なぜ今、減災が注目されるのか」「日常生活に取り入れやすい減災の工夫」について、わかりやすくご紹介していきます。
そして、日々の暮らしの中でできる“減災のヒント”を、あなたと一緒に考えていきたいと思っています。
自分や家族を守るために。
そして、もしもの時にも落ち着いて行動できるように。
今日から始められる“小さな減災”、はじめてみませんか?
減災と防災、どこが違うの?
ニュースや行政のパンフレットなどで目にする「減災」と「防災」。
どちらも災害に備えるための言葉ですが、「どう違うの?」と感じたことはありませんか?
減災と防災の違いをざっくり説明すると…
簡単にいうと、「防災」は災害を防ぐこと。
一方、「減災」は災害による被害を減らすことです。
たとえば、「崖の下に家を建てない」「堤防をつくって水をせき止める」といった、災害そのものを起こさない・被害が出ないようにするのが防災。
でも、どんなに備えていても、自然の力を完全に防ぐことはできませんよね。
そのため、災害が起きたときに「命だけは助かるように」「けがをしないように」「避難生活を少しでも快適に」という視点で被害を軽くするのが減災です。
つまり、防災は“起こさないようにする”、減災は“起きたときに備える”という違いがあります。
「減災」という考え方が生まれたのはいつ頃?
実は「減災」という言葉が広く使われるようになったのは、比較的最近のこと。
本格的に注目されはじめたのは、1990年代後半から2000年代初めにかけてです。
災害に強い街づくりや、地域防災の取り組みが全国で進められる中で、「完全に災害を防ぐことは難しい」という現実を前提に、どうやって被害を小さくするか?という発想が生まれました。
きっかけとなった出来事は?
「減災」という言葉が広く知られるようになったきっかけの一つが、1995年の阪神・淡路大震災です。
多くの住宅が倒壊し、火災が発生。6,000人以上の方が亡くなりました。
このとき、行政の救助が届く前に、多くの命を救ったのは、近所の人たちによる“共助”の力でした。
その後も、2004年の新潟県中越地震や、2011年の東日本大震災など、大規模災害が続いたことで、「どんなに備えていても想定外は起きる」「それでも命を守るための工夫が必要だ」という考えが、より広く共有されるようになったのです。
「減災」は、一人ひとりができる“小さな備え”の積み重ねです。
それは特別なことではなく、「家具を固定する」「避難場所を確認しておく」といった、日常に取り入れられることばかり。これくらいなら、自分にもできると思いませんか?
これからの時代は、「防災」+「減災」の視点で、自分と大切な人の命を守っていきたいですね。
今、減災が注目される理由
ここ最近、「防災」だけでなく「減災」という言葉を耳にすることが増えてきました。
では、なぜ今、「減災」がこれほど注目されているのでしょうか?
その理由は、大きく次の2つにあります。
異常気象と“想定外”の増加
毎年のように発生する記録的な大雨や台風、地震。
「100年に一度」と言われるような災害が、まるで毎年のように起きていると感じませんか?
気候変動の影響もあるといわれていますが、これまでの想定を超える災害が当たり前になりつつあります。
「ハザードマップで安全だったはずの地域が浸水した」
「短時間に一気に降る雨で避難が間に合わなかった」
こうしたケースも、全国で多発しています。
このような“想定外”にどう備えるか。
それが、今「減災」が注目されている大きな理由のひとつです。
高齢化社会と“自分で守る”意識
また、もうひとつの理由は、少子高齢化が進む中で、災害時に支援を待つだけでは立ち行かない現実があるからです。
たとえば、避難所への移動が難しい高齢者。無理をして避難をすれば途中でケガをしたり、最悪の場合、命を落としたりする可能性があります。
私も高齢の両親と同居しているため、他人事ではありません。避難中にケガをしたり、命を落とすようなことがあっては困ります。
それを防ぐためにも、「自宅でどう備えるか」「地域とのつながりをどう作っておくか」など、一人ひとりが日頃からできる“減災”の工夫が求められています。
とくに私たち60代前後は、これから支援を受ける側になるかもしれませんし、地域で支える側になることもある世代。
だからこそ、自分や家族、そして地域の命を守るためにも、「減災」という考え方がとても大切なんですね。
減災の具体例
「減災」と聞くと、なんだか難しそうに感じてしまうかもしれません。
でも実は、すでに私たちの身の回りでも、たくさんの“減災”が実践されているんです。
たとえば、こんなものがそうです。
- 学校の耐震化:子どもたちが通う学校では、地震に強い建物にすることで被害を抑える取り組みが進められています。
- 河川の堤防強化や治水工事:大雨のときに川があふれないように、事前に整備が行われています。
- 避難情報の早期発信:気象庁や自治体が、危険が迫る前に避難指示を出すことで、逃げ遅れを防ぐ努力がされています。
また、町内会や自治会などで行われる防災訓練や見守り活動も、まさに地域レベルでの減災と言えます。
つまり、減災とは「災害を完全に防ぐこと」ではなく、「被害をできるだけ小さくすること」。
そのために、個人・地域・行政がそれぞれの立場で備えることが求められているのです。
家庭でできる減災の工夫
では、私たち一人ひとりの暮らしの中でできる“減災”には、どんなことがあるのでしょうか?
ちょっとした工夫でも、いざというときに大きな差を生むことがあります。
ここでは、家庭で今すぐ始められる3つのポイントをご紹介します。
1. 家の中の安全チェック
地震で大きな被害を受けるのは、実は家具の転倒や物の落下によるケガが多いと言われています。
- タンスや食器棚に転倒防止グッズをつける
- 寝室にはなるべく大きな家具を置かない
- 出入口をふさぐような場所にモノを置かない
これらを意識するだけで、自宅が“避難所”としての役割を果たせるようになります。
2. 非常用品・備蓄の見直し
防災リュックや非常食の準備はもちろん大事ですが、「備えたままで安心」になっていませんか?
- 賞味期限が切れていないか
- 飲料水は足りているか(1人1日3L × 3日分が目安)
- 持病がある人の薬や医療品はそろっているか
こうしたチェックを年に1〜2回習慣にするだけで、災害時の安心感は格段に変わります。
特に持病がある方は、普段飲んでいる薬があるだけで安心感が違います。
私は東日本大震災の際に薬を持っていなくて不安な一夜を過ごす羽目になったので、それ以来、どこへ行くにも薬を持ち歩くようになりました。これも減災のための方法の一つです。
3. 家族や地域とのコミュニケーション
いざというときに慌てないためには、「どこに避難するか」「どうやって連絡を取るか」を普段から話し合っておくことも大切です。
万が一の際に安否確認ができないと、不安なまま過ごさなければいけません。メールやSNS,災害用伝言板など、複数の連絡手段を用意しておくことをおすすめします。
また、ご近所とのあいさつや立ち話も、実はとても大事な減災。
「◯◯さん、今日は見かけないけど大丈夫かしら?」
そんな声がけひとつで、助かる命があるかもしれません。
内閣府のサイトには「減災のてびき」というページがありますので、
一度見てみるのもよいのではないでしょうか。
まとめ
「減災」とは、被害を“ゼロにする”のではなく、“できるだけ小さくする”という考え方。
そして、それは行政だけでなく、私たち一人ひとりの暮らしの中でも取り組めることです。
ほんの少しの工夫と、周囲とのつながり。
それが、もしもの時に「やっておいてよかった」と思える“安心”につながります。
大きな備えは難しくても、「今日からできる小さな減災」を、あなたの暮らしにも取り入れてみませんか?
あなたの家は安心ですか?