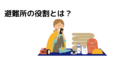地震や台風、大雨による災害…。最近は、いつどこで起きてもおかしくないと感じることが増えてきましたね。
そんな中で「備蓄って、何日分用意すればいいの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
今回は、家庭での備蓄の目安や、ムリなく始めるコツをご紹介します。
なぜ「何日分」かが大切なの?
災害時、すぐに支援物資が届くとは限りません。特に地震や大規模な風水害のあとでは、道路の寸断や交通の混乱で数日間孤立するケースもあります。
実際、国土交通省の調査によれば、東日本大震災では「一部地域の避難所では食料が地震発生から一週間が経っても全く届かない」といった問題があったことが報告されています。
これは、津波による車両の流失をはじめ、マンパワーの絶対的な不足や燃料油の不足、ガレキによる道路の不通などにより、避難所まで物資を輸送することが難しかったことが原因として考えられます。
このようなことから、最低でも3日分、できれば7日分の備蓄が推奨されています。
家庭で備える目安は?
以下は、総務省や内閣府などの推奨を参考にした一般的な備蓄の目安です。
- 水
1人1日3リットル × 家族人数 × 日数分
例:2人暮らしで7日分 → 42リットル
- 食料
レトルト食品、缶詰、乾パン、フリーズドライなど、火や水がなくても食べられるものを中心に備蓄しましょう。
アレルギーがある方はアレルギー対応食を用意しておくと安心です。また、普段から食べ慣れているものを加えることも考慮しておくとよいでしょう。
- トイレ用品
簡易トイレ(1人1日5回程度)
→ 2人×7日=70回分を目安に。
- その他の生活用品
ラップ(食器を汚さず使える)、ウェットティッシュ、常備薬、生理用品、ティッシュ、ゴミ袋など。
ムリなく始める備蓄のコツ
災害時用として販売されている、長期保存が可能な非常食のセットなどもありますが、用意したことで安心し、気づいたら賞味期限が過ぎていたということもありえます。
「ローリングストック法」を活用しよう
普段使う食材や日用品を、少し多めに買っておき、使ったら買い足す方法です。
これなら特別な準備も不要で、ムダなく備蓄できます。
収納場所を分けておく
キッチン:日常的に使う備蓄(缶詰や水など)
押し入れ:非常時用の備蓄(トイレ、ライト、乾電池など)
玄関や車:持ち出し用の非常持ち出し袋や防災リュック
自分に合った「日数分」を見つけよう
高齢の親と暮らしていたり、ペットがいたりすると、必要な備蓄も変わってきますよね。
また、自治体によっては「1週間以上の備蓄」を呼びかけている地域もあります。
【東京備蓄ナビ】では、家族の人数、性別、年代を入力すると、3日分の備蓄品と数量を計算してくれます。一戸建てかマンションか、ペットの有無なども設定できます。表示された内容は印刷しておくとよいでしょう。
表示された内容を参考に、あなたの生活スタイルに合わせて、少しずつ備えていくことが大切です。
まとめ:備蓄品は3日分から7日分を目安に用意しよう
備蓄品は最低3日分、できれば7日分以上が目安です。水・食料・簡易トイレを中心に備えましょう。特に、簡易トイレは在宅避難をする際にも必要となります。
食料や日用品は、普段の生活に取り入れているものを「使いながら備える」がコツ。
「備蓄」と聞くと大がかりに感じるかもしれませんが、できることから始めれば大丈夫。
未来の自分や家族のために、今日から一歩だけ踏み出してみませんか?
その時が来る前に、避難所のことを知っておきましょう。
⇒避難所の役割とは?50代・60代が備えておきたい避難のポイント